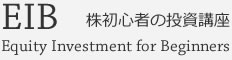証券取引では、株価の変動幅を一定の範囲内におさめるために、「値幅制限」を設けています。
その設定されている値幅制限いっぱいまで売買された状態を、「ストップ高」「ストップ安」と呼びます。
「ストップ高」「ストップ安」は、投資家の資産を守るための安全装置
買っていた株が「ストップ高だった!」というときの投資家は満面の笑みを浮かべているはずです。
「ストップ高」とは、最高の値上がりを見せた状態をいうからです。
多くの証券取引所では予想外の暴騰や暴落での混乱を防ぐため、「値幅制限」のシステムを用意しています。
どんなに売り手(買い手)が殺到しても、値幅制限の範囲内でしか売買は行われません。
値幅制限の上限価格を「ストップ高」、下限価格を「ストップ安」といいます。
制限された値幅は、前日の終値を「基準値」として計算されます。
値幅は株価によって変わり、
- 1株1000円~1500円未満:±300円
- 1株1500円~2000円未満:±400円
- 1株2000円~3000円未満:±500円
- 1株3000円~5000円未満:±700円
- 1株5000円~7000円未満:±1000円
といったように決められています(2019年現在)。
株価水準が高くなるほど、値幅制限が大きくなります。
ストップ高が起こるのは、買い手が多く、売り手が少ないときです。
値幅制限の上限価格に買い注文が積み上がった状態を、「ストップ高に張り付いた」といいます。
張り付いたまま大引けを迎えたときは、「比例配分」が行われます。
ストップ高に張り付いてしまうのは、売り注文に対して買い注文が圧倒的に多いことが原因です(ストップ安の場合は逆)。
アンバランスな注文を公平に成立させるための方法が比例配分です。
会員証券会社に公平に株数を割り振りますが、「時間優先の法則」は無視され、「成行注文優先」で判断されます。
割り振られた株は証券会社が顧客に割り当てますが、その方法は時間優先、抽選などさまざまです。
ストップ安でも売れないことがある
株価が急落するケースを考えてみましょう。
株価が通常の値動きを超えて暴落するのは、「買い手不在」「売り手殺到」という状態です。
製品の不具合、重大な事故、民事再生法の申請など、企業価値を大きく損なうニュースがでたときです。
株を保有している投資家が最も恐れているのが「寄らずのストップ安」です。
スキャンダルなどで寄付きから売りが殺到すると、一度も寄らないままストップ安で大引けを迎えることがあります。
「いくらでもいいから売りたい」と思っても、売買が成立するのは比例配分の恩恵を受けられた人だけです。
新興株バブル崩壊のきっかけとなったライブドアへの強制捜査は2006年1月でした。
翌日の取引では、買い注文の100倍を超える売り注文が殺到しました。
5日連続で寄らずのストップ安が続きました。
「3日連続でストップ安が続いた翌日には値幅制限が2倍に拡大される」ルールが適用されたこともあり、696円の株価は156円まで下落しました(その後55円まで下落)。
ちなみに連続ストップ安記録は、20連続の光通信株(2000年3月31日~4月27日)です。
なお、ニューヨーク証券取引所や香港証券取引所には値幅制限の制度がないため、1日で株価が10分の1以下になる可能性もあります。
僕は昔、保有していた銘柄がストップ安で売ることが出来ず、寝込んでしまったことがある

ずいぶん昔の話しですが、僕は持っていた株が「とある情報」によってストップ安まで売られたことがあります。
「その会社が暴力団と関係していた」という、かなりタチの悪い情報でした。
情報が出たあと、もちろんすぐに成行で全株売り注文を入れていたんですが、その日はストップ安に張り付いたまま、約定することはありませんでした。
そして翌日も前場では寄り付かず、いったい自分の資産がどこま吹き飛ぶのか分からない状態に…。
今までサラリーマンをしながら苦労して貯めてきたお金が、自分では何も出来ないまま、急激に減っていくのをただ見つめるしかありませんでした。
そうこうしているうちに、だんだんと気分が悪くなってきて、ついにはベッドで寝込んでしまったんです。
結果的には、その日の後場には売り注文が約定したんですが、当然ながら投資資金は大きく毀損してしまいました。
ストップ安になった原因が原因だけに、自分としてはどうしようもないことではあったんですが、それ以降はトラウマというか、「売りたいのに売れない状況」ほど恐ろしいものはないと、今でも思っています。
このことも、以前「僕はFXで稼いだ資金を株で長期投資している」で書いたように、僕が株の短期トレードを止めて長期投資派に「鞍替え」した理由のひとつです。
長い投資人生の中には、このようにストップ安に捕まって苦しい思いをさせられることもあれば、逆に運良くストップ高に乗れたこともあります。
ともあれ、これから株を始めようという方には、
株というものは、値幅制限に捕まれば、ひとりの投資家にはどうすることも出来ないことがある
ということを頭の片隅に留めておいて欲しいと思います。
✅ 人気・実力ともに間違いないネット証券
- GMOクリック証券 | 手数料が格安!
※ 10万円までの手数料が95円!信用取引の定額なら10万円までなんと0円!まずはおさえておきたい証券会社。 - DMM株 | 口座開設が早い!
※ 最短で当日に口座が開設され翌日にはIDとパスワードが送られてくる。手数料も最安値級。 - マネックス証券 | 外国株に強い!
※ アメリカ株と中国株合わせて3000銘柄以上を売買できる!日経が不調の時でもチャンスを見つけられるかも。 - SBI証券 | 口座開設数国内ナンバー1!
※ 僕もメインで利用してる日本で最も人気のある証券会社。初心者はとりあえずSBI証券に口座を開設しておきましょう。