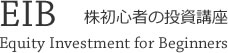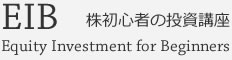僕たち株式投資家が、普段、株の取引をしていて「株式市場と証券取引所の役割」について考えることはほとんどありませんが、知識として知っておくことで、何らかの形で投資に役立つかもしれません。
例えば、ここでお話しする間接金融や直接金融の言葉の意味や、企業が上場する際の審査基準などについて、ある程度の知識があるだけで、経済や株式に関するニュースに対する理解度が変わってきます。
株式市場の役割【経済の流れは間接金融から直接金融へ】
間接金融と直接金融には、それぞれメリットとデメリットがありますが、高度成長期のように国と銀行と企業がしっかりと結びついていた時代と現在とでは、企業の資金調達方法の流れにも変化が見られます。
間接金融・直接金融
企業が、銀行から融資を受けることを間接金融といいます。
預金者のお金が銀行を通して企業に流れるからです。
株式の場合は、株を発行する企業が直接、投資家からの資金を受け入れるので、直接金融といいます。
上場企業の場合は、企業と投資家の間に証券会社が仲介役として介在します。
証券会社は、企業から株や社債を売る際の手数料、投資家からは株を売買する際の手数料や口座開設後、さまざまな取引をしてもらうことでメリットを得ます。
株を発行し、資金を調達した企業は、その資金を使って事業を営みますが、利益が上がれば配当の形で投資家に還元し、利益が上がらないときは分配しません。
しかし、株主にさまざまな通知をしたり、取引所で株の出来高に応じて費用を支払う必要があるので、株主資本の調達にも、その維持管理にもコストはかかります。
企業は、資金を調達する際に、経営上やコスト面で直接金融、間接金融のどちらにメリットがあるのかを検討します。
高度経済成長を支えた間接金融
高度経済成長時代の日本では、経済の主役は銀行でした。
銀行は私たちが預金したお金をまとめて企業に貸し出すことで、お金の流れをコントロールしていたのです。
預金者である私たちは、元本を保証され、約束の金利をもらえましたが、預けたお金がどう使われるのか知ることができません。
これは企業にとっても同じです。
資金の出してと直接向かいあうことはなく、銀行に金利を払ってお金を借りていました。
たとえ銀行が倒産しても、損をするのは銀行だけです。
貸す、貸さないの判断は、すべて銀行が担います。
このスタイルを間接金融といいます。
間接金融が中心だった日本では企業の面倒は、メインバンクが見るものと言う風習が残っています。
企業サイドも、銀行に気にいられるように役員を受け入れる等の努力を続けてきました。
マーケットが主役の直接金融
これに対して直接金融は、資金を提供する人と、提供してもらう人が直接やり取りするのが特徴です。
見知らぬ企業への資金提供をスムーズに行うために用意されたのが、株式市場です。
良いと思った企業には、市場を通じて株を購入することで気軽に資金を提供できます。
ダメだと思ったら、手持ちの株を売却するだけです。
売買をスムーズに行うには、買いたい人、売りたい人の注文を1カ所に集める必要があります。
そんなマーケットとしての機能を担うのが、証券取引所です。
日本を代表する東京証券取引所での取引には、外国人を含めた様々な投資家が参加し、1日で数兆円の株取引が行われます。
かつては市場部員が手でサインを出して行っていた売買は、売買高の増加に対応するため、現在はコンピューター化されています。
株式が企業の価値を決める
企業経営者は、株価を高くするために日々努力をしています。
経営者自身がその企業の株をたくさん持っているという事情もあるでしょう。
しかしそれよりも大切なのは、株価が企業の実力を表す物差しになっていると言う現実です。
株価が安ければ、他者に買収される恐れがあります。
また、新しい株を発行して資金を集めるのも難しくなります。
直接金融が主役の時代になり、企業はIR活動に力を入れるようになりました。
より多くの人に、より高い値段で株を買ってもらうために、投資家の一人ひとりに向けて情報を公開し、魅力をアピールする努力が欠かせません。
それだけ投資家の存在が大きくなったとも言えます。
証券取引所の2つの役割

証券取引所は、「発行市場」と「流通市場」という、2つの機能を併せ持っています。
また、企業を取引所に上場させるということは、「投資家に対して、この企業は投資に値する」というお墨付きを与えることでもあることから、「企業を審査する機関」であるとも言えます。
2つの機能を持つ証券取引所
企業が証券取引所に上場する最大のメリットは、マーケット(市場)を通じて資金が調達できる点です。
証券取引所が資金調達の場としての役割を担っています。
新たに株式を発行してマーケットで売却すれば、その代金は企業のものとなります。
大量の株式を売却するには、マーケットが不可欠です。
新たな有価証券(株券や債権など)で、投資家を募集する場を「発行市場」といいます。
これに対して、すでに発行された有価証券の売買を行う場所を「流通市場」といいます。
このように、証券取引所には、発行市場と流通市場の2つの顔があります。
上場する企業の審査は取引所の役目
投資家が安心して取引するためには、対象となる企業への信頼性が欠かせません。
企業にとっての証券取引所デビューとなる「上場」にあたては、証券取引所による審査が行われます。
「上場株式○株以上、株主○人以上」といった上場基準が取引所ごとに設けられており、クリアできた企業だけが上場できます。
ただし、同じ東京証券取引所でも、一部市場と二部市場とでは違いがあります。
上場基準の厳しい一部へ上場することは、大企業の証といえます。
投資家保護の立場から、上場企業に情報の適時開示を義務付けたり、財務内容を正確に公表しないなど上場企業としての義務を怠った企業を処分したり、経営が悪化した企業に上場廃止の処分をするのも、証券取引所の仕事です。
また、インサイダー取引や株価操作などの不正取引を調査したり、問題のある取引について処分や注意喚起などの措置をとったりしています。
株取引のマーケットは全国に4ヶ所ある

株は、東京、名古屋、福岡、札幌の国内に4か所ある証券取引所の株式市場で売買されています(大阪は2013年よりデリバティブに特化)。
上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(REIT)などの取引もできます。
世界の投資家から注目される東京証券取引所
株の取引は、野菜や鮮魚のように売買されるのではなく、電子化されているので現在、株券は発行されていません。
取引も人手ではなく、すべてコンピューターで処理されます。
投資家が、証券取引所に直接、株の売買注文を出すことはできません。
注文は証券取引所に会員権を持つ証券会社を通じて行います。
注文を出すには、証券会社に口座が必要になります。証券会社は金融商品取引法に定められた第一種金融商品取引業者で金融庁に登録されています。
証券取引は取引所が開いている時間内で行われますが、法律の改正で夜間も PTS (私設取引システム)取引ができるようになり、主に夜間取引に利用されています。
日本を代表する証券取引所といえば、東京証券取引所です。
日本の株取引の8割を担い、海外からも「トウキョウマーケット」として注目されています。
東京証券取引所は「東証」と略されるほか、地名をとって「兜町」とも呼ばれます。
東京日本橋の隣接する兜町は、証券会社や投資顧問業者が密集するエリアとして賑わってきました。
しかし、オンライン取引をきっかけに、兜町離れが進んでいます。
丸の内エリアに金融機関を集中させる「丸の内金融マーケット構想」が実現すれば、兜町の名も消えてしまうかもしれません。
名古屋証券取引所は「名証」または「伊勢町」と呼ばれ、大阪取引所は「大証」または「北浜」と呼ばれています。
世界の証券取引所も目が離せない
経済がグローバル化したことで、世界各地のマーケットが連動した動きを見せるようになっています。
アメリカを代表する証券取引所であるニューヨーク証券取引所や、ハイテク企業が数多く上場するナスダック証券取引所の動きは日本の株価に大きく影響を及ぼします。
世界の主要な株式市場は、ニューヨーク、ロンドン、日本、中国、シンガポールなどがあります。
日本の株式市場は、かつてはアメリカに次ぐ規模でしたが、中国の3市場(上海、香港、深圳)の台頭や各国の証券取引所が次々と国境を越えて合併し、その都度順位が変わっています。
各国の証券取引所が競うように合併・買収を繰り返す背景には、同じ国の証券取引所同士でも上場企業の奪い合いや金融商品、デリバティブ市場などクロスボーダー取引と呼ばれる国境を越えた取引への投資家のニーズが高まっているためです。
投資家のニーズに応えることで、さらに多くの投資家を呼び込み、手数料収入が増えることで、証券取引所は、さらに競争力を高めるための買収や投資資金を得ることができます。